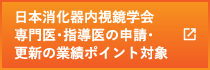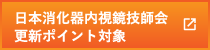演題募集
演題募集期間
2025年6月2日(月)正午 ~
7月23日(水)正午まで8月6日(水)正午まで
8月20日(水)正午まで
本会では一般演題のほか、下記のセッションの演題を募集しております。
締切日直前にはアクセスが集中してつながりにくくなる事がございますので、時間的な余裕をもってご登録ください。
発表形式
全て口演発表となります。
字数制限など
- 共同演者数:10名まで
- 所属機関数:10施設まで
- 演題名:60文字以内
- 抄録本文:全角800字以内以内
募集カテゴリー
下記より選択してください。
シンポジウム「直腸癌の前がん病変を探る」
- 司会:
-
- 藤井 隆広
- (医療法人社団隆風会 藤井隆広クリニック)
- 池松 弘朗
- (東京大学医科学研究所
先端医療研究センター 先端消化器内視鏡学分野)
<司会のことば>
直腸癌は、大腸癌全体での割合は高いが初期病変の発見頻度が低い、発見される病変は巨大なLST-G病変と小型のIIa+IIc病変が多い、発育速度が速いことが予想されるも適切な間隔内でのサーベイランス検査では直腸癌はほぼ見つからない、結腸癌と比較してリンパ節転移率は同じであるが、遠隔転移(特に肺転移)が多く予後が悪い等謎が多く存在する。前回、前々回の本学会で『直腸病変の謎に迫る』というシンポジウムが開催され、多くの議論がされたが、未だ謎の解明には至っていない。ただ、SuSa、Skirt所見等前がん病変と考えられる病変の存在も明らかにされた。そこで今回のテーマは直腸癌の前がん病変に的を絞り議論することで、少しでも直腸癌の解明に繋がればと考えている。多くの演題応募を期待する。
パネルディスカッション1「拡大内視鏡観察 観察法から診断、理論まで」
- 司会:
-
- 樫田 博史
- (川西市立総合医療センター 消化器内科)
- 佐野 寧
- (医療法人薫風会 佐野病院)
<司会のことば>
食道・胃においても拡大内視鏡は重要であるが、臓器によって手技が異なる。本セッションでは大腸における拡大観察について討議する。日常診療に使用できる拡大大腸内視鏡が市販されてから32年が経過した。拡大観察においては、単に拡大倍率を上げるだけでは有用と言えず、基本的な画像解像度や、画像強調法との組み合わせが重要である。色素を用いた画像強調や pit pattern 分類は、ほぼ完成された感があるが、非色素画像強調に関しては、未だに新しい手法が次々と誕生しており、各モダリティの意義、取捨選択や使い分けが十分確立されたとは言えない。観察の対象は主として腫瘍性病変であるが、炎症性疾患における拡大観察の意義も検討され始めている。いっぽう、拡大スコープのない施設や、あっても施設全体で1-2本しかない場合がまれではなく、十分活用しきれていない現状も存在する。また、連続的に拡大できるスコープが存在するが、いわゆる near focus のみのスコープも多用されている。
拡大観察によるリアルタイム診断は、内視鏡治療の適応や手技選択にも直結する重要な要素である。診断精度のさらなる向上には、単なる画像認識にとどまらず、病理組織学的所見との整合性や診断理論の体系化が不可欠である。本セッションでは、各施設で実践している具体的拡大観察法の手順や診断の際の視点・工夫、特徴的内視鏡所見と病理組織診断の対応、JNET分類など既存の診断法における運用上の課題や限界、新しい画像強調法の活用法、AIなど支援技術との融合、初学者に対するトレーニング法など、理論・実践の両側面からの知見を改めて共有したい。拡大内視鏡診断学の進化・深化と次世代への継承も見据え、多くの積極的な応募を期待する。(尚、症例提示も歓迎する。)
パネルディスカッション2「大腸内視鏡挿入法 軸保持短縮法とは?」
- 司会:
-
- 中嶋 孝司
- (川崎市立多摩病院 消化器内科)
- 寺井 毅
- (寺井クリニック)
<司会のことば>
1980年代後半より工藤進英先生が確立した軸保持短縮法は、その著書「大腸内視鏡挿入法 ビギナーからベテランまで」で初めて用いられた用語で、現在の大腸内視鏡挿入における標準的な手技になっている。一方で大腸内視鏡機器は、極細径から太径までの種々のスコープの存在、硬度可変、受動湾曲、高伝達挿入部、挿入形状観測装置など、挿入を援助するシステムも開発されてきた。また、先端フードや周辺機器、拡大および特殊光観察、治療内視鏡の進化も著しく、時代と共にその挿入法のスタイルも変化してきている。未だに時に挿入困難な状況におちいることもあるのが、大腸内視鏡挿入であるが、現在の多くの技術を組み合わせることで難しさを軽減することができる可能性もある。本パネルディスカッションでは、軸保持短縮法の原点に立ち返り、今の内視鏡診療におけるこの挿入法のポイントは何なのか活発な議論をしたい。各施設の軸保持短縮法における独自の工夫やその具体的方法等をご報告いただき、初学者へのメッセージも含めて、全ての大腸内視鏡医に明日の内視鏡診療のヒントになるような会にすることを考えています。
ワークショップ1「消化管3D-CT 現状と今後の展望」
※放射線科医、技師の方もふるってご応募ください
- 司会:
-
- 満崎 克彦
- (済生会熊本病院 予防医療センター)
- 鶴丸 大介
- (九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野)
<司会のことば>
近年、消化管領域における3D-CT技術の進歩は著しく、臓器の形態や病変の広がりを立体的に把握できる手法として、診断・治療の両面で重要な役割を担いつつあります。なかでも大腸CT(CT colonography)は、低侵襲で客観的な画像情報を得られる検査として再評価されており、大腸内視鏡を補完する存在として、その臨床的意義が高まりつつあります。増加を続ける大腸癌による死亡への対策としても、大腸CTの活用は今後さらに重要になると考えられます。
本ワークショップでは、消化管3D-CTに関する現状や課題、そして今後の展望について幅広く取り上げ、日常臨床に直結する情報を共有したいと考えております。技術がいかに進歩しても、ブラッシュアップされた知見が関係する医療者に十分に共有・周知されなければ、その真価は発揮されません。本ワークショップが、参加される皆様の知識と経験を結集し、診療現場における大きな推進力となるとともに、わが国の医療に新たな力をもたらす契機となることを願っております。
大腸CTに関する情報をお届けする「CTCメルマガ」を配信しています。是非ご登録ください。
https://www.radiol.med.kyushu-u.ac.jp/medicalcare/ctc/mailmagazine.html
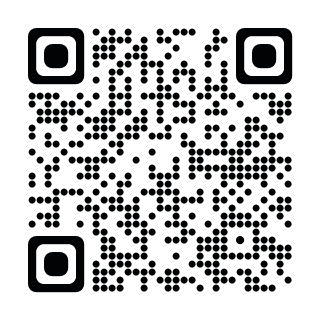
ワークショップ2「経過を追えた症例から学ぶ ー症例検討ー」
- 司会:
-
- 松田 知己
- (仙台厚生病院)
- 斎藤 彰一
- (がん研究会有明病院 消化器センター 下部消化管内科)
<司会のことば>
大腸腫瘍は上皮性と非上皮性腫瘍に大別される。腫瘍径が小さい場合や異型度が低いと予想される場合は、慎重な経過観察を選択される場合もみられる。しかしながら、その後に余儀なく内視鏡もしくは外科切除がされることもある。本セッションでは、経過観察された症例で経過が追えた病変に対して、内視鏡および病理所見で十分な検討可能な症例を登録いただき、当日、参加者で症例検討を行う予定である。なお、演題応募多数の場合は本プログラム委員で慎重に吟味の上、採用したい。
積極的な演題登録をお待ちしています。
一般演題
注意事項
- 図表の使用はできません。
- 英字および数字は、スペースを含め半角で入力してください。
- 登録された抄録に関しては、誤字・脱字・変換ミスを含め、原則として事務局では校正・訂正を行いません。
そのまま印刷されますので、登録者の責任において確認してください。
※ 所属の記載は学会事務局にて調整する場合がありますのでご了承ください。
演題採択
演題の採否通知は、2025年9月中旬を予定しております。
筆頭著者のメールアドレスに配信いたします。
応募方法
- 演題募集は、演題登録システムを利用し、本ページからのオンライン登録のみ受付いたします。
- オンライン登録システムでは、【Firefox】【Google Chrome】【Microsoft Edge】【Safari】の各最新版で動作確認を行っております。
- 必ずご本人に連絡ができる電子メールアドレスが必要になります。
登録演題の確認・修正・削除
- 演題登録後は、確実に登録されているか、「確認・修正画面」にて演題登録番号とパスワード、メールアドレスを用いて必ずご確認ください。
- 演題登録の受領はメールで行います。演題登録受領のメールが届かない場合は、メールアドレスの入力が間違っていることや、セキュリティ設定のため受信拒否と認識されている可能性があります。迷惑メールなどをご確認いただき、届いていない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 抄録内容の修正を必要とされない方も、念のため「確認・修正画面」にて抄録が登録されていることを確認されるようお勧めいたします。
- 演題登録募集期間中は、何度でも演題の修正が可能です。その際、演題登録時の演題登録番号およびパスワードが必要になります。
- 演題登録期間後に、演題を削除される場合は下記運営事務局までお問い合わせ下さい。
演題登録 問い合わせ
- 〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-10 三翔ビル4F 株式会社プランニングウィル内
- TEL:03-6801-8084 FAX:03-6801-8094
- E-mail:jsce43@planningwill.co.jp